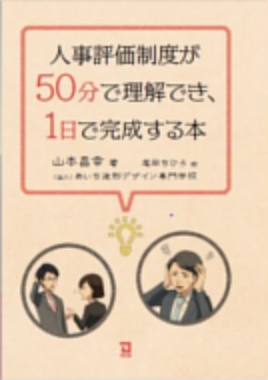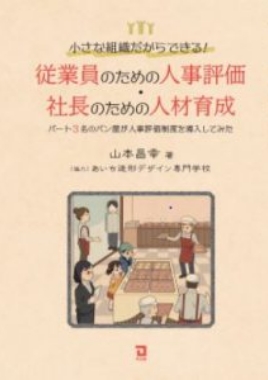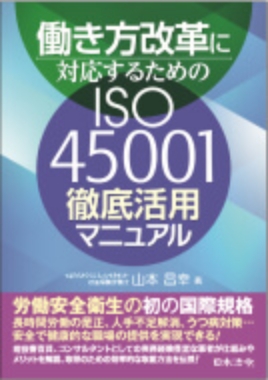ブログ
BLOG
前回から、職能資格等級制度 の説明に入りました。
今回もその続きで、既存の(一般的な)職能資格等級の問題点を視てみましょう。
職能資格等級の「職能資格定義表」は、具体的に規定すべきです。
前号では、職能資格定義には、等級ごとの能力・力量・技量を明確にし、具体的には、○○部の3等級の人材は、どのような能力が必要か、どのような力量が必要か、どのような技量が必要かを決定するのです。
その内容が非常にあいまいな組織が多いのです。
もちろん、あえてあいまいにしている組織も存在していることは理解していますが、私は、職能資格定義表は組織が人材に対して求める能力・力量・技量のハードルの一部を担うものであることを鑑みると、具体的に明確にする必要があると思います。
非常に抽象的な規定例として、営業部3等級の規定例として「営業関連業務に関する専門知識や経験を有し、企画、判断、折衝業務を行い部署目標の達成に貢献する。また、担当業務の遂行を通じて下級者に適切な指導を行う」
意味わかりますか?いや、イメージできますか?私もよくわかりません。
でも、こんな感じの規定内容をしている企業に数多く出会いました。
では、もう少しわかりやすい営業部3等級の規定例として「部下の見本となる企画書の作成を行える」
少し良くなりましたがマダマダですね。
「部下の見本となる」 とは、どのようなことでしょうか?
職能資格の定義は具体的にイメージできる内容を決定してこそ能力・力量・技量のハードルとなるのです。
あなたの会社が職能資格等級制度を導入し、「要求力量のハードル」を明確にした「職能資格等級定義表」を策定する場合は、だれがみてもイメージできる明確な内容にすべきなのです。
例えば、建設業の場合
・5千万円までの「施工計画書」が一人で作成できる
・建設機械の特定自主検査が実施できる
・2級建設施工管理技士の資格取得
・公共工事現場の安全パトロールが実施できる
など。
執筆者 山本昌幸プロフィール:
人事制度(人事評価制度、賃金制度)指導歴28年超の専門家、特定社会保険労務士。
商業出版書籍に「人事評価制度が50分で理解でき、1日で完成する本 (忙しい社長のためのビジネス絵本) 」(同友館)、「今日作って明日から使う中小企業のためのカンタンすぎる人事評価制度」(中央経済社)、「従業員のための人事評価・社長のための人材育成」(同友館)、「人手不足脱却のための組織改革」(経営書院)、「『プロセスリストラ』を活用した真の残業削減・生産性向上・人材育成実践の手法」(日本法令)等がある。
「人事制度(人事評価制度・賃金制度)セミナー・勉強会」の講師を160回以上努め、社長・経営層の延べ受講生1600名以上。
自らの約10名の従業員を雇用する組織の経営者。